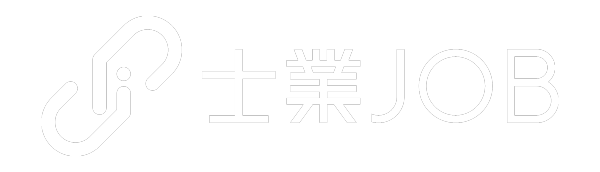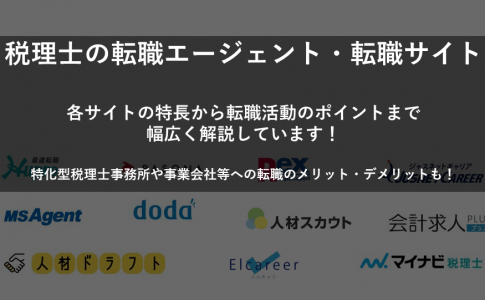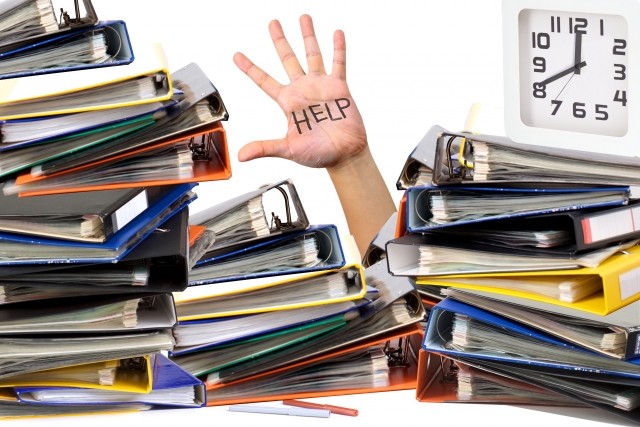税理士業界で働く方々は全般的に転職回数が多い傾向にあり、いくつもの会計事務所を渡り歩いたという人も少なくないです。
こうした情報は多くの方がご存じなのですが、これから税理士を目指す方にとってはこうした情報をネガティブに捉える(働きにくいブラック会計事務所が多いから転職回数が多い等)方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。
今回は転職が多くなる理由について見ていきたいと思います。
税理士の転職理由で多いものは?
税理士業界では転職が多いです。その理由をこれから5つ解説します。
税理士という仕事の特徴や勤め先の特徴など様々な理由で転職を考える方がいます。事前に把握し、業界の特徴を把握しましょう。
スキルアップ志向が高い、独立のために必要な経験を得るために転職が増える
税理士試験勉強中の際は試験勉強に理解のある会計事務所で勤務したいという方が一般的ですが、税理士試験に突破し、税理士登録するようになるとキャリアに目を向ける方が多くなります。
一通り法人税務を経験した後プラスアルファで自身の強みを身に着けていくため(例えば資産税等)に何をすべきか考え始める方が多くいらっしゃいますが、そうした自分の武器を身に着け高めていくために必要な経験を得るため他の事務所へと転職されるケースが非常に多いです。
この繰り返しになる傾向にあります。
勤務する会計事務所ごとに得意とする業務が異なるのでどうしても必要な経験を得ようと思ったら転職をする必要が出てくるので転職が多くなる傾向にあると言えます。
また、将来独立を考えているというケースも多いため、独立に備えて経験しておきたい事をするために転職するケースも多くなっています。
こうした前向きな理由での転職はかなり多い傾向にあり、転職によってキャリアアップしていくことが可能な職種であり、必ずしも転職回数が多いからといって転職で不利になる職種ではありません。
ただ、一般的な職種の方々と同様に不自然な短期離職が多かったり、整合性が取れない転職が多いと単に根気がない方とみられて転職で不利になるケースもあります。
将来性の不安
将来の不安と記載するとネガティブな印象を受けるかもしれませんが、後ろ向きな理由だけでなく前向きな意味も入っています。
税理士業界は高齢化著しく、所長は70代、80代といった会計事務所もそれなりにあります。
こうした事務所に勤務している方の場合、この事務所はいつまであるのか、後継ぎはどうなのかといった疑問を抱き始めます。
仮に後を引き継ぐ方がいても、方針の変更なども考えられます。その方針に従っていけるかなども将来性の不安につながり、安定した事務所への転職を考え始める方も多くいらっしゃいます。
その他、取り扱っている業務が記帳や申告等の単純な業務ばかりという会計事務所では、自身のスキル向上に対する不安と事務所そのものの将来性の不安から転職を検討される方もいらっしゃいます。
入力代行が主である税理士事務所に勤めている場合、単純作業の繰り返しであることも多いです。税理士の資格を取ってもキャリアアップが望めない場合があります。もっと自分のスキルを磨くことができる会計事務所への転職を考えるケースもあるでしょう。
先程記載したようにスキルアップ志向が高い方も多いので、向上心から不安を感じるケースがあります。
業界全体でみれば伸びていて将来性の高い事務所も多いので、そうしたところへ転職を考える税理士の方も多くいらっしゃるという背景が一つあります。
労働条件の不満
税理士は高度な専門知識が必要とされる仕事ですが、「年収が低い」「各種手当が物足りない」という会計事務所はそれなりにあります。
また会計事務所は確定申告時期や決算が集中する時期など繁忙期には毎日終電で帰宅など、拘束される時間が長くなります。労働条件の不満から転職する人も一定数いらっしゃいます。
所謂ブラック会計事務所は減少傾向ですが、個人事業主が多いので、体制整備がまだ進んでいない事務所もそれなりにあるため転職時は一定の注意も必要です。
ブラック会計事務所に転職しないためにの記事などもご参考ください。
会計事務所内の人間関係
会計事務所は少人数であるところが多く、所長税理士や長く働いている番頭さんの影響力があります。代表税理士や上司との相性が良くなければ、職場の人間関係に疲弊して転職に繋がるケースがあります。
こうした事務所ばかりではありませんが一定数あるので情報収集をしっかりせずに転職活動をして無意味に転職回数が増える方もいらっしゃいますのでご注意ください。
税理士業務に適性を感じなくなった
税理士の仕事はお金にかかわることであり、地道な作業が続きがちです。業務でミスがあるとクライアント事業に大きく影響し、場合によっては会計事務所が損害賠償を求められるケースにまで発展します。
数字が苦手な場合や経理や財務の仕事に魅力を感じなければ、税理士業務を続けることに自信を無くし、別領域へ転職を検討される方もいらっしゃいます。
会計事務所の採用ニーズが高いことも転職が多い理由となる
近年、会計事務所の仕事が増えているにもかかわらず、税理士の成り手が減少しています。そのことから、採用ニーズが高まっています。それが故に転職すること自体のハードルが比較的低く、それも転職が多いことの要因となっていると考えられます。
税理士試験の受験者数が減少
税理士試験といえば難関資格の1つに数えられますが、受験者数は年々減少しています。令和元年度の税理士試験申込者数(延べ人数)は5万5,000人であり、平成26年度の7万9,000人に比べ、2万人以上減少しており、多少の増減はあるでしょうが大まかな傾向は今後も変わらないものと考えられます。
会計事務所の大型化が進み、採用ニーズが高まったことから小規模事務所からの転職が増えた
昨今、会計事務所の大型化が進み、従業員も数百名規模の事務所が増えてきました。これらの大型事務所は採用ニーズが高く、就業環境も「残業時間の減少」「産休・育休制度の導入」「効率化の促進」など、良い人を採るための努力を重ねています。間口も広いので零細会計事務所からの転職者も一時期増えました。
20代〜30代の若手税理士は特に重宝される
税理士の受験者が減少したため、20代~30代の若手税理士は会計事務所の就職市場では大変貴重な存在です。
また、かつては「税理士有資格者」や「税理士試験の合格科目〇〇以上」と採用ハードルの高かった会計事務所が「会計実務未経験」でも採用するケースがあります。
税理士は経験次第で需要が大きく変わる
税理士はAIにとって代わられると言われており、将来性がなさそうなことを数年前から言われていますが、現状はむしろ逆に需要が高まっており、かなり稼げる職種の一つとなっています。
「選ばれる税理士」になるために努力は必要ですが、クライアントに貢献できることを追求できれば、今まで以上に魅力ある仕事になるでしょう。そして、そのためのスキルを身に着けるために転職回数が増えている傾向にあります。
現在勤務している会計事務所に不満があったり、もっとスキルアップできる環境へ転職したいとお考えのケースでは転職エージェント等に相談してみるのも良いでしょう。
多くの税理士の転職支援を行っている実績からあなたにマッチする会計事務所の紹介が受けられます。